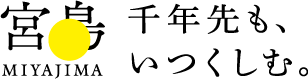広島の大学生が考える
未来へつなぐ宮島の在り方。
宮島の観光や伝統的建造物について研究したり、島内の地域活性化に取り組んだりと、広島の複数の大学の学生たちが、「宮島」をテーマにさまざまな活動を続けている。そんな学生同士の交流、学生と地域住民の交流の場を設け、産学官民による連携・協力体制を整えることを目的に、初の試みとなる「宮島学生フォーラム」が2025年2月18日(火)に開催された。当日のイベントに密着し、学生たちの声に耳を傾けた。
「宮島エクスカーション」
町家通りを訪ね、歴史・文化を知る。

午前の部「宮島エクスカーション」では、広島大学・広島修道大学・安田女子大学の17人が宮島の町家通りへ。訪ねたのは、明治時代の終わり頃に建てられた町家を改装し、16年前から一棟貸しの宿を営む「厳妹屋(いつもや)」だ。オーナーの菊地寛さんが、宮島の町家特有の間取り(建物入口からミセ・オウエ・ザシキという3部屋が並んでいること)や、敷地の内部に配置されている中庭などについて、建物を案内しながら説明してくれた。

続いて、築200年以上の杓子(しゃくし)問屋の建物を改装し、2003年からギャラリーカフェを営む「ぎゃらりぃ宮郷(みやざと)」を訪問。店主の宮郷哲弥さんからは、宮島の町家建築の特徴や昔の生活の様子、島内住民と連携した地域活性化への具体的な活動についても話を伺った。


参加した安田女子大学の学生は、「これまで町家通りにあまりなじみがなかったけれど、伝統的な建物の中を見られて貴重な体験になりました」「宮島独特の文化や暮らす人の思いを知られてよかったです」と話す。

左から、2年生の谷口花穂さん・箱崎渚さん、3年生の豊田祥子さん。
「宮島学生フォーラム」
学生が考える宮島の課題解決とは?

午後の部「宮島学生フォーラム」では、宮島の研究活動・地域活性化プロジェクトに携わる広島大学と広島修道大学の学生が、これまでの成果を発表。会場には大学生や高校生、地域の方など50人以上が集まった。
広島大学からは、大学の地域貢献事業「地域の元気応援プロジェクト」で、中江町(ちゅうえまち)を拠点に活動してきた宮國真菜さん、田中萌乃さん、中川直人さんが登壇。
「宮島における日本人と外国人旅行者の行動の違い」について発表したのは宮國さん。日本人旅行者が同行者との時間を大切にし、外国人旅行者は文化や自然との触れあいや多様な観光体験を重視することを紹介。地域密着型のアクティビティを充実させれば、旅行者の滞在時間・行動範囲が拡大し、宮島全体のオーバーツーリズムの解決につながるのではと提言した。

「他大学の発表や宮島の方の話を聞いて、プロジェクト内容に共通部分が多いことが分かりました。
今後、連携して活動できる機会が増えればいいなと思います」
田中さんは、「宮島観光におけるアクセシビリティ(観光スポット・観光体験へのアクセスのしやすさ)」をテーマに、観光客の分散化について発表。嚴島神社参拝後に他のスポットを訪ねやすい案内MAPの作成や、表参道商店街と並行する海岸通りへ人の流れを分散させてはどうか、といったアイデアを紹介した。

「自分の研究に対して、地域の方からフィードバックがあったことが一番の成果です。
地元の人ならではの視点、率直な思いに触れることができて勉強になりました」
中川さんの研究は、「重要伝統的建築物の活用について」。中江町に多く残る伝統的な建物とそこでの生活体験そのものが観光資源になることに着目している。空き家を宿泊施設へ活用することで、歴史ある建物に泊まり昔の暮らしを肌で感じてもらい、弥山に登ることで島に根付く自然信仰も体験してもらうことを提案した。

「研究してきた内容が、思いのほか島内ですでに行われている活動と重なっていたので、
もう少し具体的な提案ができたらよかったなと思います。
空き家活用など、今後も宮島の課題に向き合っていきたいです」
これからの宮島を共に創っていく。
学生フォーラムの最後を締めくくったのは、広島修道大学の「地域つながるプロジェクト」で活動する後藤直志さん・岸達哉さんの発表「中江町と考える新しい体験型宮島観光」。
宮島の中でまだ認知度が低い「中江町」を、宮島の第3の観光拠点として盛り上げることを目標にしている。同プロジェクトでは「やさしい日本語」を用いたフリーペーパーの作成・配布や、「ちゅうえマルシェ」「たのも船づくりワークショップ」などのイベントを企画・運営している。「アンケート調査によると、宮島を訪れる外国人も地域の人たちも、互いにコミュニケーションを求めています。私たちが手段と場所を提供することで、双方のニーズが満たされ、島民と学生のつながりも深くなると思うんです」と後藤さんは話す。

広島修道大学 国際コミュニティ学部3年 岸達哉さん(左)
「今日のフォーラムなどをきっかけに、同じ考えを持つ学生と
地域住民が協力して活動を続けていけば、きっとすごいことが起こるはず。
宮島エクスカーションで巡った伝統的建造物への興味も深まりました」
それぞれの発表の後には、宮島に暮らす人たちから多様な質問・感想が寄せられた。中でも印象的だったのは、「混雑する表参道商店街は、具体的に数値化してもらえれば、海岸通りの活用の目安になるのでは?」という意見。「研究内容に対するフィードバックがあったことが収穫でした」と、声を受けた田中さんも振り返る。宮島について考える学生と地域住民の声が熱く交わった。
そのほか「宮島びいきなひと」と題して、ゲストハウス三國屋・寺澤潤哉さん、宮島ろくろ作家・下村祐介さんの講話や、参加者全員によるワークショップも開催。




最後は、学生と地域住民の皆さんによる「“宮島びいき”交流会」を実施。学生たちは、地元の皆さんや事業者の皆さんから、こういう機会にしか聞けない話を伺い、発表内容についても議論しあいました。

学生も地域住民も、それぞれの視点で宮島の課題に真摯に向き合い、豊かな未来を願っている。「宮島学生フォーラム」は、その実現に向けた確かな足掛かりになったようだ。